集合場所は東京メトロ湯島駅。
天気は上々、爽やかな秋の空です。
折角だつたので湯島天満宮をちょっとお参り。
2023年10月21日 秋の小旅行「湯島上野界隈を歩く」はこんな感じでした。


湯島天満宮へのアプローチには男坂と女坂というものがありました。
男坂からの入口に気になる石碑が。「講談高座発祥の地」とありました。
【文化4年(1807年)、湯島天満宮の境内に住みそこを席場としていた講談師伊東燕晋が、家康公の偉業を読むにあたり、庶民と同じ高さでは畏れ多いということを理由に、高さ
三尺一間四面の高座常設を北町奉行小田切土佐守に願い出て、これが許された。これが
高座の始まり】
との説明がなされていました。
江戸時代では、こんなことにもお上の了解を得る必要があったのですね。
当宮の境内こそ我が国伝統話芸 講談高座の発祥の地である
と力強く結ばれています。
湯島天満宮が学問の神様とは別な顔を持っていたとは・・・・

境内の南壁付近にちょっと変わった形の石碑が。「努力」という文字が読み取れました。
なんと王貞治氏の【努力碑】という代物です。
「同氏の生涯の座右の銘である「努力」の文字を記すことによりもって若者の亀鑑とするもの」として昭和53年1月1日に建立されています。
「亀鑑」とは聞きなれない言葉でした。
広辞苑で調べたら「行動の基準となる物事、かがみ、てほん」とありました。

湯島天満宮から春日通の北側は東京大学を始めとする学問の地域ですが、
宮の南側の細道をちょっと入るとそこは平成はおろか一気に昭和時代に
タイムスリップしたような景色に出くわしました。
なんとも言えないこの乱雑とも表現される風景ですが、何故か漠然とした
統一感を感じてしまいます。

さて、10時になりました。
湯島天満宮の北側、学問と文化の地域での散歩の始まりです。
まずは東京都の都立文化財9庭園のうちのひとつ、
旧岩崎邸庭園からスタートです。

庭園もさることながら、旧岩崎邸の豪華さといったら、本当にビックリです。
建物内部の撮影は禁止だったのでここに画像で紹介することができないのが残念です。
南に面した広々としたベランダは1F客室と大食堂、2Fは同じく客室と並びは集合室と
記載がありました。岩崎家の人々は洋館に繋がる和館にて生活していたようですが、
当時はこの洋館をしのぐ建坪550坪を超える規模を誇っていたそうです。
邸宅ならびに庭園は明治29年(1896年)に岩崎彌太郎の長男で三菱第3代社長の久彌の
本邸として造られました。
往時は1万5千坪の敷地に20棟もの建物が並んでいたとのことですが、現在は三分の一の敷地となり、現存する建物は洋館・撞球室・和館大広間の3棟のみです。
洋館から撞球室へはなんと地下道で繋がっています。この広大な館に一体何人の家族が
住んでいたのか、はたまた使用人は何人くらいいたのか気になったのですが、
その類の説明は記されていませんでした。
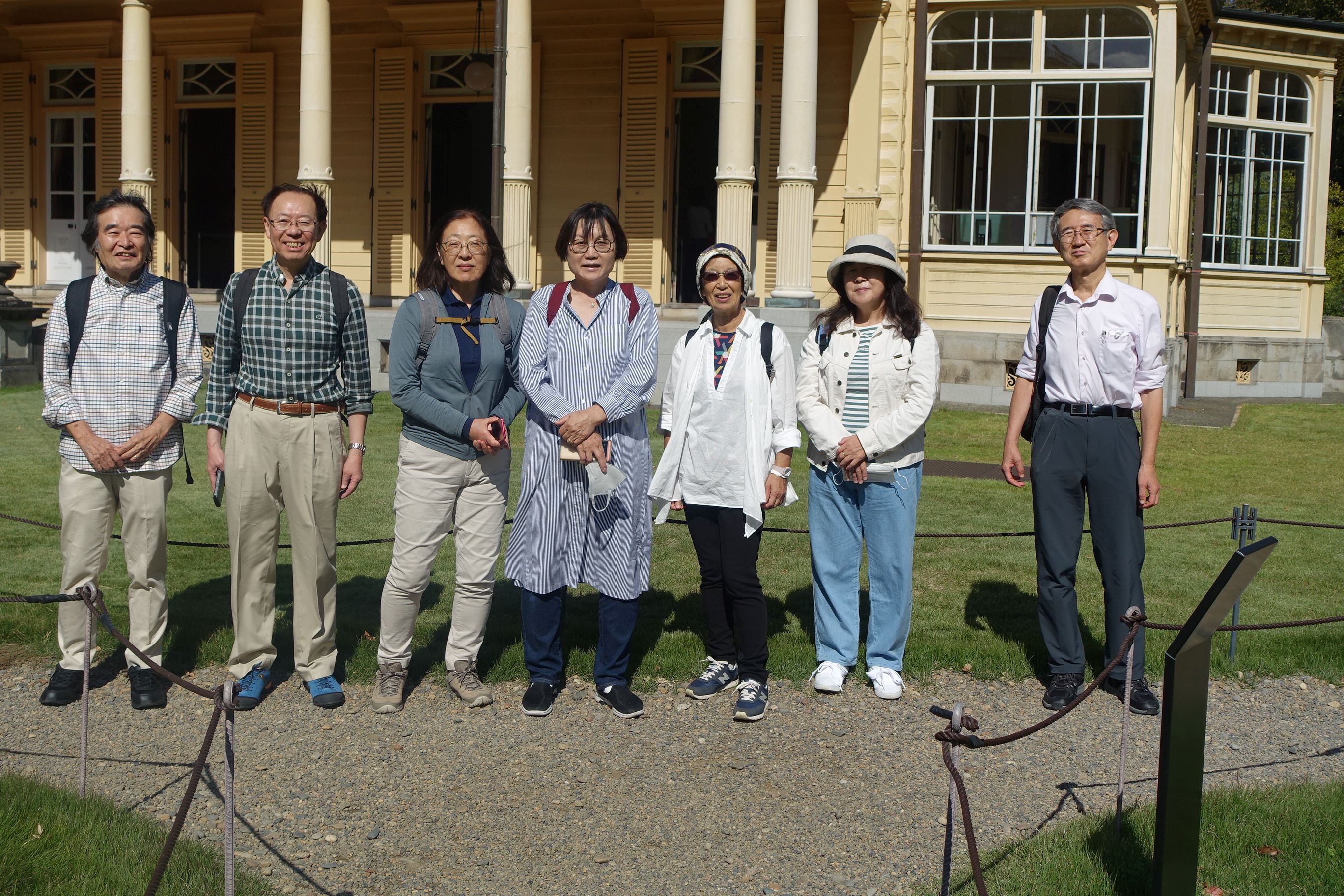
洋館前の庭園で早速記念写真を一枚。
因みに都立文化財9庭園は以下の通り。
浜離宮恩賜庭園
旧芝離宮恩賜庭園
小石川後楽園
六義園
旧岩崎邸庭園
向島百貨園
清澄庭園
旧古河庭園
殿ヶ谷戸庭園

庭園の写真は色々なところで閲覧可能ですので、ちょっと違ったアングルから。
正面に見える洋館の右側の黒っぽい建物が撞球室です。
ビリヤードといっても十分に一般の家屋よりも大きいです。
洋館の左側奥の平屋が和館です。
洋館は、主に年一回の岩崎家の集まりや外国人賓客を招いてのパーティーなど
プライベートな迎賓館として使用されていたとのこと。往時の三菱財閥の強大さが
肌で感じられます。

そこから数分歩くこと5~6分。直線距離にして300mのところに横山大観の自宅がありました。
今は横山大観記念館として内覧できます。一部のみ撮影可能でした。
この邸宅は現在では横山家の個人資産となっていますが、公益財団法人横山大観記念館として財団が運営しています。
大観は明治の時代この地を創作活動の拠点と定め、写真の部屋(2F)を仕事部屋としていました。自然光のもとでの描画にこだわっていたからだそうです。
岩崎家と横山家が近所に住んでいたとは、なんとも明治時代の浪漫を感じます。

それはそうとして
横山大観の生涯に思いを馳せながらも、ビデオを肴に一休み。
お疲れさま~。
左手前で座布団に正座してビデオ鑑賞の赤い帽子の女性は我らとは関係無い
一般入場者です、念のため。
現存するこの邸宅は昭和29年(1954年)に建て替えられたので、私たちとほぼ同い年。
畳を敷き替えたり、床の沈みの手入れをしたりで維持することは結構大変とのこと。
他人事ではありません。

中庭の設計にも大観の美意識が強く反映されているとのことです。
植栽の種類にもこだわり、さらに手入れは最小限に抑え、自然の四季折々の景色を
楽しめるようになっています。今回は残念ながら緑一色の庭でした。
記念館では数千に及ぶ作品を在庫しており、3ヵ月ごとに展示を入れ替えていることも
あり、庭の四季を愉しむ目的もあわせて年に数回訪れるリピーターは多いそうです。

時刻は11時半。健康的な一日なので、お腹が空くのも早目です。
昼食は不忍の池の周りをちょっと歩いて、老舗の和食料理屋にて。

鰻で有名なこのお店ですが、今日はリーズナブルな幕の内弁当で。
それでも一品一品は丁寧な造り。眼にも舌にも美味しく頂きました。
それにしても天ぷらに正体不明の具がひとつ。あれは一体なんだったのか・・・

エネルギー補給も済んで、さあ午後の部のスタートです。
上野公園は絶好の外出日和。大賑わいでしたが、外国人もかなり目立ってきました。

そんな中、私たち一行はちょっと変わった小団体だったかも知れません。
別に誰が気にするという訳でもありませんが。

歩いているうちに、ちょっと変わった形の石碑を発見。なんと
駅伝の歴史ここに始まる
駅伝は大正6年(1917年)奠都50周年を記念して開催されました。
初めての駅伝はスタートは京都三条大橋。
3日間をかけてここ不忍池の奠都50周年記念博覧会会場を目指したそうであります。
ブラブラ歩いているとこんな発見にも出くわします。
これが散歩の醍醐味かも知れません。
まだ散歩の途中ですが、ウキウキの気分になります。

午後の最初の目的地は上野東照宮です。

今年は大河ドラマのおかげもあり、いつになく参拝者でにぎわっていました。
この場所で一名合流予定があるため、みんな家康公そっちのけで同窓生の到着を待ちます。

東照宮の境内にたわわな実を成している柑橘系樹木を発見。
さてこれは橙? 蜜柑? 八朔? 夏みかん? と議論を深める面々。

改めまして、家康公に敬意を表し
全員集合での一枚。ご丁寧にカメラ置き場まで用意されていました。
ここでタイマー撮影をしたまでは良かったのですが、
その後普通の撮影モードに戻す操作が判らず、
シャッターボタンを押す度に5秒待ってシャッターが開くという失態が暫く続きます。

さて次の訪問先の入口で立ち往生。
引率の瀧上先生、腕組みしちゃってどうしたのかな?

目的地は東京芸術大学。旧東京音楽学校奏楽堂。
残念ながら
「本日はホール使用があるためホールおよび展示室の見学はできません」
との看板とともに
門は閉ざされたまま。
こういったアクシデントも散歩の醍醐味のひとつ。早速予定を変更して
次のアクションに移ります。
そもそも最初から「すべてこの予定で行く」などと固く考えていた輩は
ひとりもいなかったのでは。

折角ここまで来たのだから寛永寺を奉拝。
家康公の知恵袋天海大僧正によってここ江戸城の鬼門の位置に創建されました。
徳川慶喜がこの一角に幽閉されていたとのことですが、見学するには事前予約が
必要とのことでした。

次の目的地、谷中霊園に到着。早速渋沢栄一翁の墓所を参拝しました。
墓標・墓石は極めてシンプルでしたが一言で云えば巨大。
青淵澁澤榮一墓と記されてありました。青淵(セイエン)と読むそうです。
榮一翁の両脇にも墓石がありましたが、どのような縁者なのかは判りませんでした。

榮一翁の墓石をアップで。墓所内でも比較的高台に位置してあり、後ろには高層ビルが
植え込みの背後にちらっと映り、日本経済発展の礎を築いた同氏にふさわしい景色です。

そして次は徳川慶喜の墓所に。墓所は回りを鉄柵を含む壁で囲われていました。
向かって左に慶喜。右には正室の美賀子が眠っています。
澁澤翁のそばで休むことは、慶喜にとって願っていたことなのでしょうか?
イカン!、大河ドラマのせいで、吉沢亮と草彅剛の顔しか浮かんで来ない!!
とにかく今日のスタートは三菱財閥と終わり間際に澁澤榮一と明治を代表する財界人を
訪ねました。
来年は新一万円札とたくさんの良い縁起で結ばれますよう。

今回の散歩の締めくくりは朝倉彫塑館。
他の見学施設同様にこの館も館内はほとんど撮影禁止でした。
朝倉彫塑館は彫刻家朝倉文夫氏のアトリエ兼住居だった建物です。
アトリエと住居、そしてそれらを繋ぐ回廊に囲まれた中庭。中庭の中央には池とそれに浮くように巨岩で模したいくつかの島。流石美大の先生のお住まいは芸術的。
明治40年(1907年)にこの地に居を構えてから少しずつ増改築を加え昭和10年(1935年)に今の姿に完成しました。

設計には朝倉文夫氏自らが担当し、細部に至るまで同氏のこだわりが詰まっています。
東側母屋の屋根上には裸婦像が。当時の近隣住民はずいぶんと驚いたことでしょうね。

アトリエ棟は屋上に出ることが出来ます。屋上から東を見るとスカツリーも間近です。
都心なのに意外と空が広いのに改めて驚かされます。

そして屋上の西側。運動着の若者がうずくまって夕陽を眺めています。
今にも立ち上がりそうな背中の隆起した筋肉に、
時代の勢いが反映されているようにも感じられます。

そこで問題になったのが、この若者は何のスポーツの選手なのだろうか。
現場にいた説明員に尋ねると「砲丸投げです」との回答。
でも砲丸の割にはあの球はちょっと大きすぎるような。
帰りがけに入口にいたベテランぽい説明員に改めて尋ねると
「さあなんでしょうね?」とおおらかな返事。
最後の最後まで散歩の愉しみを堪能した一日でした!